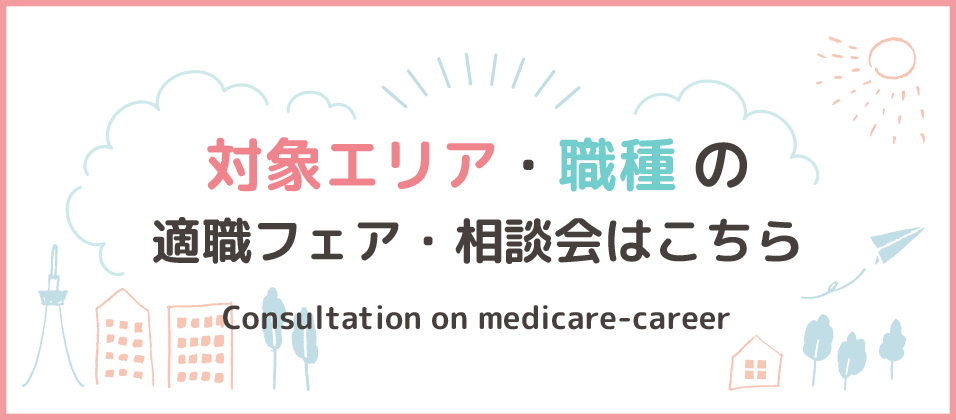介護コラム
介護福祉士になるための勉強方法を勉強時間などと共に解説
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
資格取得方法
知識
介護職

介護福祉士を目指すには、体系的な学習と計画的な勉強時間の確保が欠かせません。本記事では資格取得に向けた具体的な学習ルートや勉強方法を詳しく解説します。
護福祉士になるための勉強方法を知る前に資格取得ルートを理解しよう
介護福祉士を目指す際の学習は、選ぶ資格取得ルートによって必要な勉強内容や期間、準備の仕方が大きく変わります。現在は、いずれのルートでも介護福祉士国家試験に合格することが必須です。
代表的なルートは「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」の三つで、あなたの生活背景(働きながらか、フルタイムで学ぶか)や学習スタイル(通信中心か、通学中心か)に合わせて選べます。
ここでは、各ルートで身につく力、必要な学習、試験への接続の仕方を具体的に押さえ、後の勉強方法の最適化につなげます。
実務経験ルートで介護福祉士を目指す勉強方法
実務経験ルートは、介護保険サービス事業所や障害福祉サービス事業所などで介護職として働きながら、受験資格を満たしていく方法です。原則として「通算3年以上かつ540日以上の実務経験」に加え、「介護職員実務者研修(450時間)」の修了が必要です。
現場での身体介護・生活支援・認知症ケア・コミュニケーション支援の実践と並行して、学科知識や介護過程(アセスメントから評価まで)の体系立てを行う勉強が求められます。
働きながらの学習となるため、シフトに合わせたスケジュール管理、eラーニングやスクーリングの計画的な受講、過去問の短時間反復学習が合格の鍵となります。未経験者は、入口資格として介護職員初任者研修から学習を始めると用語理解や基本技術の習得に役立ちます。
実務者研修とは?学習内容と期間
実務者研修は、介護福祉士国家試験の受験資格となる標準450時間の研修で、通信学習(テキスト・eラーニング)と通学スクーリングを組み合わせて実施されます。学習内容は、介護の基本、尊厳の保持と自立支援、コミュニケーション技術、発達と老化の理解、認知症の理解、生活支援技術、介護過程、医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養の基礎的知識と演習)、感染予防、リスクマネジメント、倫理・法令遵守、チームケアなど、国家試験の出題基準と連動した構成になっています。
受講期間は受講ペースや通学日程により異なりますが、働きながらの場合はおおむね6〜12カ月程度の計画を立てる人が多く、保有資格や履修状況に応じて一部科目免除が適用される場合もあります。
スクーリングでは、移乗や体位変換、口腔ケア、排泄・入浴支援などの技術を安全管理とセットで演習し、現場で役立つ手順書や記録の書き方も学びます。
実務者研修修了後の介護福祉士国家試験対策
実務者研修で学んだ知識と技術を国家試験の筆記対策に接続することが重要です。厚生労働省が定める出題基準を確認し、科目横断で問われる状況設定問題に対応できるよう、介護過程の各段階を事例と結びつけて整理します。過去問題は最新年度から遡って複数年分を反復し、解答根拠をテキストにマーキングして知識をネットワーク化します。
法令や介護保険制度の改正点は頻出のため、最新情報を確認してください。働きながらの学習では、平日は30〜60分の短時間学習で用語・数値・制度のインプットを進め、休日に模擬試験や分野別演習で得点力を測ると効率的です。受験申込時には、実務経験日数の管理や実務者研修修了証明書、実務経歴証明書の準備が必要になるため、早めの確認が安心です。
養成施設ルートで介護福祉士を目指す勉強方法
養成施設ルートは、指定の介護福祉士養成施設(専門学校・短期大学・大学など)で体系的に学び、卒業により介護福祉士国家試験の受験資格を得る方法です。多くは2年制(昼間部)で、既修者向けの1年課程が設置されている場合もあります。
基礎理論から実習までをパッケージで学べるため、フルタイムで学習に集中したい人、学内・学外の指導体制のもとで段階的に力をつけたい人に適しています。授業・演習・実習が連動しており、記録の書式やケアプランの立案、チームカンファレンスの進め方など、現場直結の学びが得られるのが特長です。
介護福祉士養成施設での学習内容と期間
カリキュラムは、介護の基本、生活支援技術、介護過程、こころとからだのしくみ、認知症の理解、障害者支援、医療的ケア、総合演習、実習(施設・在宅)などで構成され、国家試験の出題範囲を網羅します。演習では、移乗・ポジショニング・摂食嚥下支援・排泄支援等の手技を安全確保の視点とともに磨き、グループワークで事例検討(アセスメント、目標設定、モニタリング)を重ねます。
介護実習は特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所・訪問介護など複数のフィールドで行い、利用者理解、家族支援、多職種連携を体験的に学びます。期間は学校ごとに異なりますが、標準的には2年間で、通学授業に加え自学自習の時間(予習・復習・レポート作成)を計画的に確保することが、国試対策にも直結します。
養成施設卒業後の介護福祉士国家試験対策
養成施設で学んだ体系知識を国家試験に最適化するには、分野別の弱点補強と状況設定問題への対応力強化が要点です。過去問題の正誤判断にとどまらず、なぜ他の選択肢が不適切かを根拠づける学習で理解を深めます。
直前期は模擬試験で得点の波を確認し、法令・制度・用語の最終整理を行います。多くの学校では補講や国試対策講座、教員による個別相談が用意されるため、就職活動と並行しながら計画的に活用すると効果的です。実習経験は状況設定問題での判断根拠に活きるため、体験を言語化して「観察→仮説→介入→評価」の流れで説明できるように整えておきましょう。
福祉系高校ルートで介護福祉士を目指す勉強方法
福祉系高校ルートは、福祉科や介護福祉コースのある高等学校で所定のカリキュラムを修了し、国家試験の受験資格を得る方法です。基礎から段階的に学べるため、高校段階で早期に専門性を育てたい人に向いています。
定時制・通信制で福祉を学べる学校もあり、学び方の選択肢が広いのが特徴です。学内学習と臨地実習を通じて、生活支援技術、認知症ケア、コミュニケーション、福祉と法制度、情報活用、リスクマネジメントなどを身につけ、卒業後の就職・進学・受験勉強へとつなげます。
福祉系高校での学習と卒業後の選択肢
福祉系高校では、介護基礎、生活支援技術、こころとからだのしくみ、介護総合演習、福祉情報、介護実習などを段階的に学びます。授業では記録の書き方や介護過程の考え方を基礎から身につけ、実習で利用者理解や多職種連携の基礎を体験します。
卒業後は、介護現場に就職して実践を積みながら国家試験に挑む、介護福祉士養成施設や短期大学・大学に進学して専門性を深める、いずれの選択も可能です。高校在学中から過去問題に触れて出題形式に慣れ、用語集やまとめノートで基礎用語を整理しておくと、卒業後の学習がスムーズになります。
介護福祉士国家試験の受験資格と対策
福祉系高校ルートでは、指定された教育課程を修了し卒業することで介護福祉士国家試験の受験資格を得ます。国家試験は年1回実施される筆記試験で、科目横断の理解が求められるため、高校で学んだ基礎科目を出題基準に沿って再整理することが重要です。卒業後は、最新の過去問題と模擬試験で出題傾向に対応し、介護保険制度や関連法令、医療的ケア、認知症の理解、介護過程と生活支援技術を重点的に復習します。
実務に就く場合は、勤務シフトに合わせて平日のインプットと休日の演習を分担し、学校で培った記録力と観察力を状況設定問題の根拠説明に結びつける練習を重ねると効果的です。なお、このルートでは原則として実務者研修の修了は必須ではありませんが、補完的に受講することで現場での即戦力や国家試験対策の理解が一層深まります。
介護福祉士国家試験の勉強方法と合格への道のり
介護福祉士国家試験の概要と試験科目
介護福祉士国家試験は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが実施する年1回の国家試験で、現在は筆記試験により実施されます。出題はマークシート方式の多肢選択式で、知識だけでなく事例を読み解く総合的な理解力が問われます。
試験科目は「人間の尊厳と自立」「人間関係とコミュニケーション」「社会の理解」「介護の基本」「コミュニケーション技術」「生活支援技術」「介護過程」「発達と老化の理解」「認知症の理解」「障害の理解」「こころとからだのしくみ」「医療的ケア」といった分野で構成され、科目横断の事例問題(総合的な出題)も含まれます。
出題範囲は、介護保険法、障害者総合支援法、高齢者虐待防止法、個人情報保護に関する基本、権利擁護(成年後見制度等)、地域包括ケアシステム、多職種連携、ICF(国際生活機能分類)、介護過程(アセスメント・計画・実施・評価)、生活支援技術(移乗・体位変換・口腔ケア・排泄・更衣・入浴・褥瘡予防・拘束の適正化)、感染症対策(標準予防策・手指衛生)、リスクマネジメント、認知症ケア(BPSD への理解や非薬物療法)、終末期ケア(ターミナルケア)、医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養に関する安全管理や観察)など広範です。
最新の受験案内や細部の実施要項は毎年度公表されるため、公式の情報で確認して学習計画に反映しましょう。
介護福祉士国家試験の難易度と合格率
本試験は、現場経験がある方には日々の実務と結び付けて理解しやすい一方、法律・制度、医学的基礎、倫理・権利擁護などは体系立てた学習が必要で、総合力が問われます。合格基準は毎年公表され、総得点に対して一定の基準点が設定されます(難易度により調整されます)。
合格率は年度により変動しますが、一定の学習時間を確保し、出題傾向に沿った対策を行えば十分に到達可能なレベルです。重要なのは、事例問題で根拠をもって選択肢を切り分けられる理解の深さと、科目横断で知識をつなぐ力を養うことです。
独学で介護福祉士国家試験に合格するための勉強方法
独学の基本は「出題範囲の全体像を把握→良質なテキストでインプット→過去問題でアウトプット→間違いの原因分析→弱点の再インプット→模擬試験で時間配分を含めた総仕上げ」というサイクルを繰り返すことです。
特に法律・制度は図解で構造を掴み、生活支援技術や感染対策は「なぜその手順になるのか」を安全性・倫理・リスクマネジメントの観点で理解します。事例問題は、ICFの枠組みや介護過程に基づいて「情報収集→アセスメント→目標→具体的支援→評価」の流れで考える癖をつけると正答率が上がります。
過去問を徹底的に活用する勉強法
過去問は出題傾向の縮図です。まずは直近数年分を科目別に解いて論点を把握し、次に年度別で本番さながらに時間を計り実施、最後に間違えた問題を「なぜ誤答したのか」「正答を導く根拠は何か」を根拠レベルまで言語化します。
選択肢ごとに誤りの理由(法律名・定義・手順・倫理)を書き分けると応用が効きます。年度横断で同テーマの出題を集めて比較すると、繰り返し問われるキーワード(例:権利擁護、標準予防策、身体拘束の適正化、インフォームド・コンセント、QOL、BPSD、地域包括ケア)が浮かび上がるため、重点化が可能です。
効率的な暗記法と理解を深めるポイント
知識定着には、間隔反復(スキマ時間での反復)、アクティブリコール(隠して思い出す)、要点の音読や図解化、ミニケースを自作して適用する練習が効果的です。
介護保険制度の仕組み、要介護認定の流れ、成年後見制度の類型、虐待の類型と通報義務、事故発生時の初期対応、標準予防策の具体、移乗・体位変換・ポジショニングの留意点、認知症の中核症状とBPSDの違い、ターミナルケアにおける意思決定支援などは頻出テーマです。単なる丸暗記ではなく、ICFや介護過程に結び付けて「なぜそれが適切か」を説明できるようにしましょう。
通信講座や予備校を活用した介護福祉士の勉強方法
学習時間が取りづらい方や独学で伸び悩む方は、通信講座や通学型の対策講座を併用することで、最新の出題傾向・法改正に即した教材、質問対応、模擬試験、学習スケジュールの伴走支援などのメリットを得られます。自分の弱点に合う講座を選び、課題提出と復習のサイクルを固定化することで学習効率が高まります。
通信講座のメリットと選び方
通信講座の強みは、動画解説や添削、質問サポート、法改正アップデート、模擬試験などの一体型サポートにあります。選定時は、テキストの体系性と図解の分かりやすさ、過去問解説の根拠の深さ、スマホ対応の学習システム、学習スケジュール機能、質問対応のスピード、模試・直前対策の充実度を確認しましょう。資料請求で見本を確認し、自分に合う説明のレベル感かどうかを見極めることが大切です。
通学予備校のメリットと効果的な活用法
通学型は、講師に直接質問できること、学習のペースメーカーになること、仲間と切磋琢磨できることが大きな利点です。通える日程の短期集中講座や土日講座を選び、受講前にテキストを予習、受講後48時間以内に過去問で関連論点を解き直す「予習→受講→即復習」の型を徹底すると定着度が高まります。職場や地域の研修会、専門学校の公開講座、社会福祉法人等の勉強会も有用なので、参加できる機会を学習計画に組み込みましょう。
介護福祉士国家試験対策の勉強時間とスケジュールの立て方
スケジュールは試験日からの逆算が基本です。長期(基礎固め)・中期(過去問回転)・直前(模試と総仕上げ)の三段階に分け、週単位で「いつ・どの科目を・何を使って・どこまでやるか」を具体化します。働きながらでも継続できるよう、平日は短時間のアウトプット中心、休日にまとまったインプットと復習という配分にするのが現実的です。
学習の可視化のために、進捗表やチェックリスト、正答率の推移、弱点リストを更新し、定期的に計画を見直してボトルネック(進んでいない科目・時間帯)を潰します。
働きながら勉強時間を確保するコツ
まず生活リズムに合わせて固定枠(例:朝の30分、通勤中、休憩の10分、寝る前)を先にカレンダーに確保し、スマホ学習や音声学習を組み合わせてスキマ時間を積み上げます。集中を高めるために、学習前のルーティン(机を整える・タイマー設定)と短時間集中法(ポモドーロ・テクニック等)を取り入れ、終わったら翌日のToDoを1つだけ残しておくと継続が容易です。
家族や上司に受験を宣言し、残業やシフトの配慮、試験前の休暇取得などの環境調整を早めに行うと安定して学習時間を捻出できます。睡眠と体調管理は記憶定着に直結するため、無理な詰め込みよりも毎日の小刻みな継続を重視しましょう。
試験までの学習計画と模擬試験の活用
計画の骨子は「過去問の回転数と復習の質」「模試での客観評価」「法改正の最終チェック」です。まず主要科目を一巡してから直近の過去問に着手し、二巡目以降は正答でも根拠が曖昧な問題にしるしを付け、根拠を明文化します。模擬試験は少なくとも本番形式で複数回受け、成績表の分野別データから弱点科目を明確化し、翌週の学習配分を変える材料にします。
本番想定で開始時間・休憩・解く順番・見直し手順までリハーサルし、時間切れや焦りを防ぎます。直前期は法改正点、頻出論点、誤答が多いテーマ(権利擁護、感染対策、身体拘束の適正化、介護過程の展開、認知症の対応、医療的ケアの安全管理)に絞って総仕上げを行い、知識の穴を最小化します。
介護士の勉強を継続するためのモチベーション維持のヒント
目標設定と進捗管理で勉強のモチベーションを保つ
介護士が勉強を継続するためには、まず「なぜ介護福祉士を目指すのか」を言語化しておくことが土台になります。利用者のQOL向上に貢献したい、専門性を高めて職場で信頼されたい、処遇やキャリアパスを広げたいなど、自分の価値観に根ざした理由をメモにして学習ノートの冒頭に貼っておくと、忙しい時期でも原点に立ち返れます。
次に、長期・中期・短期の3層で目標を設定します。長期は試験日から逆算した合格目標、中期は月ごとの単元達成や過去問の回転数、短期は1週間・1日の具体的なタスクです。例えば「今月は人間の尊厳と自立・介護の基本を終わらせ、週末に過去問1年分を解く」のように、期限・量・到達基準を明確にします。SMART(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)に沿って言い換えると、実行しやすくなります。
進捗は「見える化」して管理します。学習カレンダーやチェックリスト、学習記録アプリ・紙の学習ノートを使い、勉強時間、過去問の正答率、模擬試験の振り返り、理解度(◎◯△)を日々記録します。連続学習日数をカウントする「習慣チェーン」を作ると、途切らせたくない心理が働き継続力が上がります。
シフト勤務に合わせたスケジュール設計も要です。シフトが出た日に1週間分の「学習ブロック」を先に予定表へ確保し、夜勤前は軽い暗記や音声学習、夜勤明けは休養と短時間の復習、休日はまとまった過去問演習や模擬試験にあてるなど、時間帯ごとの適性に合わせます。予定は7〜8割の達成を目安に余白を残し、崩れたら週次でリスケする「柔軟な計画」を前提にします。
集中を高める技術として、ポモドーロ・テクニック(25分学習+5分休憩)やタイムブロッキング(科目ごとに時間を固定)を活用します。開始のハードルを下げるため「机に座ってテキストを開く」「過去問を1問だけ解く」といった超小さな第一歩を事前に決めておくと、自然にエンジンがかかります。通知オフ・タイマー・学習環境のルール化など、環境から集中を支援する工夫も有効です。
週次レビューでは「計画どおりできたこと/できなかったこと」「理解が浅い単元」「次週に改善する1点」を必ず書き出します。調子が落ちたときは、目標の過密・方法のミスマッチ・睡眠不足など原因に応じて、タスク量の圧縮、教材や勉強法の見直し、休養の挿入を行い、小さな達成に対しては自分へご褒美を設定して内発的動機づけを強化します。
息抜きとリフレッシュで集中力を維持する
継続には休息の計画も不可欠です。学習スケジュールに最初から休憩やオフ日を組み込み、回復を意図的に行います。短い休憩では、肩・首のストレッチ、深呼吸、水分補給、目のリラックス(遠くを見る)などのアクティブレストが効果的です。立ち仕事や移乗介助で身体に負担がかかりやすい介護現場だからこそ、体をほぐす休憩は学習効率の観点でも優先度が高い行動です。
睡眠は最重要の投資です。夜勤がある場合は分割睡眠や仮眠を取り入れ、まとまった睡眠が取れる日は就寝・起床時刻を大きくずらし過ぎないようにします。就寝前はスマートフォンやテレビを控え、ぬるめの入浴で体温を一度上げてから下げると眠りやすくなります。夜勤前後の勉強は、暗記カードや音声学習など負荷の軽いメニューに切り替えると継続しやすくなります。
食事とカフェインの使い方も見直します。血糖値の乱高下を避けるため、たんぱく質や食物繊維を含む軽食を取り入れ、カフェインは就寝の十分前から控えめにします。水分補給をこまめに行うだけでも、頭痛や倦怠感が減り集中が持続します。
ストレスマネジメントとして、学習ノートに「できたこと3つ」を毎日記録し、自己効力感を育てます。腹式呼吸や短いマインドフルネス、軽い散歩は自律神経を整えやすく、模擬試験や過去問で思うように点が伸びない時期の気持ちの切り替えに役立ちます。疲労が強いと感じたら、1〜2日を完全休養日にして心身を回復させ、翌週の計画を少し軽くして再始動する勇気も大切です。
不眠や食欲低下、強い不安が続くなど生活に支障が出る場合は、無理をせず医療機関や職場の相談窓口に早めに相談しましょう。健康を守ることは、働きながら介護福祉士国家試験に挑む上での最優先事項です。勉強は「全力で走る時期」と「立て直す時期」を波のように設計し、小さな達成を積み重ね続ければ、忙しい介護士でも合格に必要な勉強時間と質を安定的に確保できます。
まとめ
介護福祉士は国家資格であり、キャリアアップや処遇改善につながる大切な資格です。効率的に学ぶためには、計画的な勉強時間の確保や参考書・問題集の活用がポイントとなります。働きながら学ぶ場合でも無理なく続けられる学習方法を取り入れることで、知識と技術を高められます。
メディケアキャリアで
北信越の介護職求人を探す
関連記事
-
未経験でも介護士として働くことは可能?
介護福祉士
ケアマネージャー
仕事内容
知識
介護職

更新日:2026年01月29日
この記事では、未経験者が歓迎される理由や仕事内容、資格取得のステップ、職場選びのポイントまでをわかりやすく解説します。
詳しく読む
-
病院に勤務する介護士の仕事内容とは?
介護福祉士
ケアマネージャー
仕事内容
知識
介護職

更新日:2026年01月23日
この記事では、病院勤務の介護士の具体的な仕事内容、日勤・夜勤の流れ、多職種との連携、他施設との違い、必要な資格やスキル、キャリアパスなどを解説。
詳しく読む
-
介護職に復職した時に最大40万円もらえる再就職準備金とは?
介護福祉士
ケアマネージャー
お金
知識
介護職

更新日:2026年01月23日
本記事では再就職準備金制度の概要や申請方法、注意点を詳しく解説します。
詳しく読む
-
介護士はどの年齢層が多い?年代別の特徴や働き方の違いなども解説
介護福祉士
ケアマネージャー
知識
介護職

更新日:2026年01月23日
この記事では、年代別の特徴や働き方の違い、施設形態・雇用形態による傾向を詳しく解説します。
詳しく読む
-

更新日:2026年01月29日
未経験でも介護士として働くことは可能?
介護福祉士
ケアマネージャー
仕事内容
知識
介護職
この記事では、未経験者が歓迎される理由や仕事内容、資格取得のステップ、職場選びのポイントまでをわかりやすく解説します。
詳しく読む -

更新日:2026年01月23日
病院に勤務する介護士の仕事内容とは?
介護福祉士
ケアマネージャー
仕事内容
知識
介護職
この記事では、病院勤務の介護士の具体的な仕事内容、日勤・夜勤の流れ、多職種との連携、他施設との違い、必要な資格やスキル、キャリアパスなどを解説。
詳しく読む -

更新日:2026年01月23日
介護職に復職した時に最大40万円もらえる再就職準備金とは?
介護福祉士
ケアマネージャー
お金
知識
介護職
本記事では再就職準備金制度の概要や申請方法、注意点を詳しく解説します。
詳しく読む -

更新日:2026年01月23日
介護士はどの年齢層が多い?年代別の特徴や働き方の違いなども解説
介護福祉士
ケアマネージャー
知識
介護職
この記事では、年代別の特徴や働き方の違い、施設形態・雇用形態による傾向を詳しく解説します。
詳しく読む
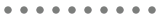

 0800-222-6155
0800-222-6155

 0800-222-6155
0800-222-6155