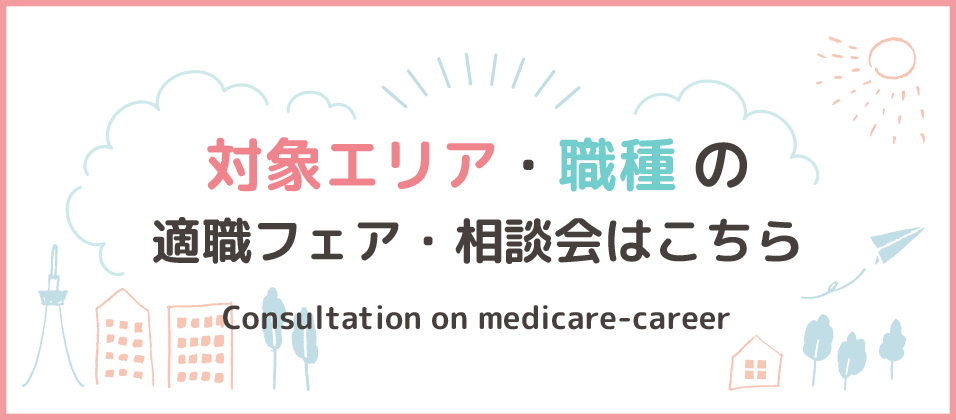介護コラム
介護施設での利用者から暴言や暴力などハラスメントにどのように対処するか紹介
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
介護事務
知識
介護職
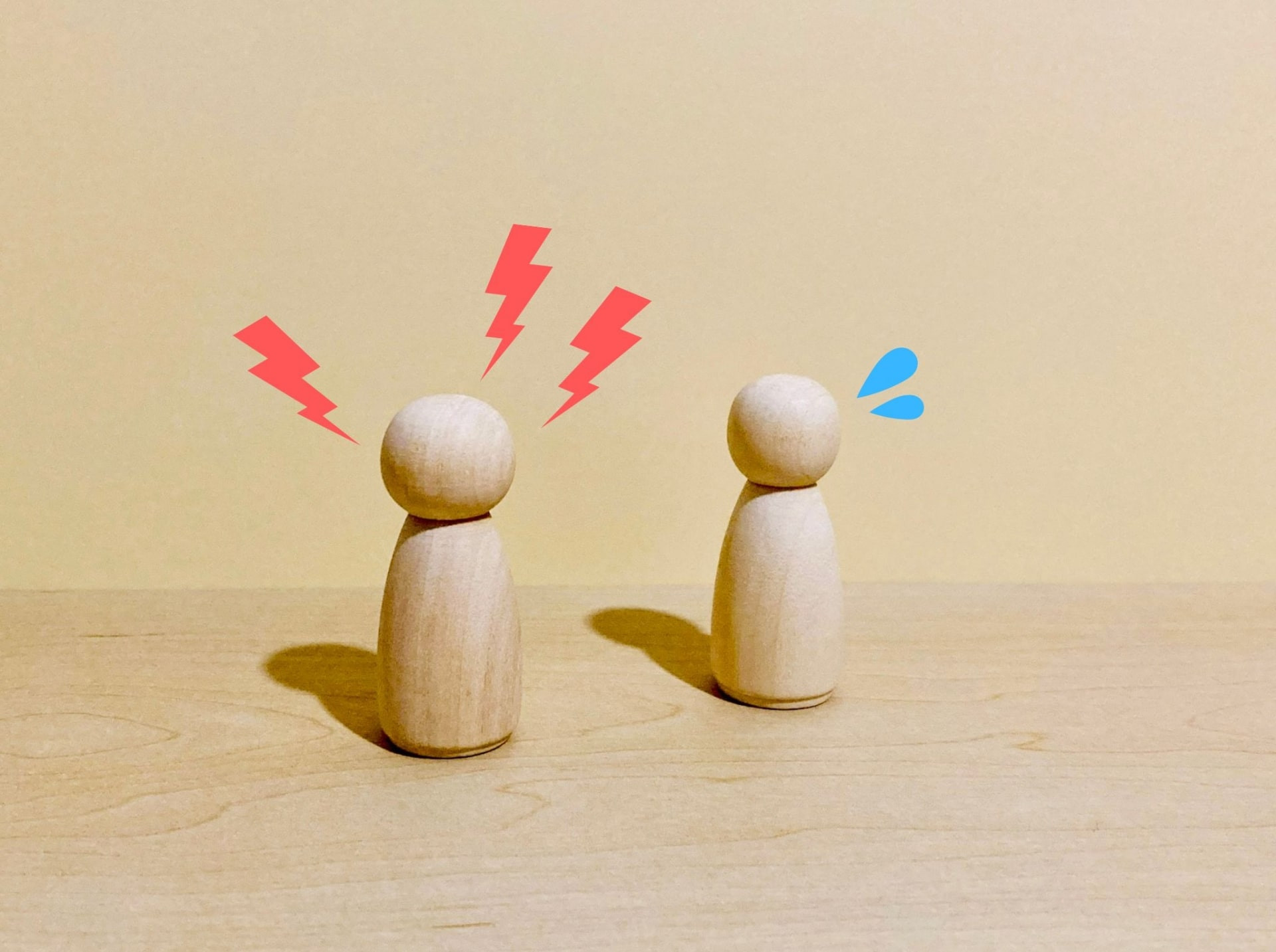
介護現場では、利用者からの暴言や暴力といったハラスメントが深刻な問題となっています。介護士は暴言や身体的・性的ハラスメントに日常的にさらされ、精神的負担が蓄積しやすい状況にあります。本記事では、なぜこのような行為が発生するのかという背景を踏まえたうえで、介護士が安全に働き続けるための初期対応や報告の仕方、職場全体で取り組むべき予防策やセルフケアの重要性について詳しく解説します。
介護現場で介護士が直面する暴言やハラスメントの現状
介護士が利用者から受ける暴言や暴力の種類
介護士が日常的に直面する言語的暴力には、「死ね」「ばか」「うるさい」などの罵声や大声での怒鳴り声が含まれます。身体的暴力としては、手を振り払われる、引っかかれる、強く押される、場合によっては殴る・蹴るなどの行為が発生し、思わぬケガや身体的リスクを伴うことがあります。
また、性的ハラスメントとして不適切な身体接触や下品な発言を受けるケース、さらには執拗な視線やプライバシー侵害にあたる言動も報告されています。これらは心理的負担を増大させ、働き続けるモチベーションや精神的健康に深刻な影響を及ぼします。
なぜ利用者からの暴言やハラスメントが発生するのか
認知症の症状によるもの
認知症患者は幻覚・妄想や短期記憶の障害により、介護士を他者と混同したり、「盗られた」「裏切られた」といった錯覚に陥ることがあります。これが原因で過度に攻撃的な言動をとる場合があり、言語的・身体的な暴力行為を引き起こす要因となります。
精神疾患やその他の病気の影響
統合失調症や双極性障害、うつ病などを抱える利用者では、感情コントロールが難しくなることがあります。幻聴・幻覚による不安やイライラが増幅し、突然の暴言や暴力に至るケースが少なくありません。
環境への不適応や不満の表れ
入所生活の変化や他利用者とのトラブル、プライバシーの不足などがストレスとなり、不満を抱える利用者もいます。狭い居室や騒音、食事内容への不満が積み重なると、それらを介護士にぶつける形でハラスメントが発生しやすくなります。
介護士とのコミュニケーションのすれ違い
言葉かけのタイミングが合わない、意図をくみ取ってもらえないと感じると、利用者は不安や苛立ちを覚えます。説明不足や敬語表現の不一致、体調変化への対応遅れなどのすれ違いが、暴言や暴力行為を誘発することがあります。
介護士が暴言やハラスメントを受けた際の初期対応と報告の重要性
暴言を受けたその場で取るべき初期対応
冷静さを保ち距離を取る
利用者からの暴言や大声によるハラスメントを受けた際、まずは自分の感情をコントロールし、可能な限り落ち着いた態度を維持しましょう。身体的リスクを避けるために一定の距離を確保し、無理に反論せず安全な距離を保つことが重要です。
第三者に助けを求める
暴言や暴力行為がエスカレートしそうな場合は、すぐに近くの同僚や上司、場合によっては他の専門職(看護師や医師)に助けを求めてください。複数人で対応することで、利用者の興奮状態を和らげ、安全確保と認知症や精神疾患による混乱を早期に把握できます。
感情的にならずに状況を記録する
その場で可能な範囲で、時刻、発言内容、利用者の様子や周囲の状況を簡潔にメモします。後で報告書や記録帳に詳細を残す際に、事実関係を正確に再現できるよう、感情的にならず冷静な視点で記録を心がけましょう。
施設内での報告と情報共有の徹底
上司や同僚への速やかな報告
初期対応が落ち着いたら、すぐに担当リーダーや施設長に状況を報告します。口頭と文書の両方で伝えることで、事後対応やケアプランの見直し、ハラスメント防止策の検討が迅速に行われる体制を整えましょう。
暴言の内容と状況を詳細に記録する
発言の正確な言い回し、利用者の認知症の進行度合いや表情、起こった時間・場所などを報告書に記載します。感情的表現を排し、客観的な事実に基づいた記録を残すことがトラブル防止と後日のアセスメントに役立ちます。
チーム全体での情報共有と連携
報告書をもとに定期的なミーティングやカンファレンスを開催し、ケアマネジャーや看護師、リハビリ職など関係者間で情報を共有します。チームで連携してケアプランや環境整備を検討し、再発防止に向けた具体策を立案しましょう。
利用者からの暴言やハラスメントを繰り返さないための具体的な対策
個別ケアプランの見直しと環境調整
利用者の状態に合わせたケアの検討
認知症の進行度や身体機能の低下、BPSD(行動・心理症状)の有無を定期的にアセスメントし、ケアプランを更新します。たとえば、言葉の理解力が低下している利用者には短文でゆっくり話す、痛みや不快感が原因の場合は医療スタッフと連携して鎮痛や整形外科的ケアを検討します。
また、レクリエーションや日常生活動作(ADL)の支援を細分化し、達成感を得やすいタスクに調整することで、利用者の自尊心を維持し、フラストレーションから来る暴言を予防します。
ストレスを軽減する環境整備
色彩や照明、音量といった環境要因は利用者の心理状態に大きく影響します。自然光の取り込みや間接照明の活用で落ち着いた空間を作り、騒音を防ぐために防音カーテンや吸音パネルを設置します。
家具配置は視覚的にわかりやすく動線を確保し、転倒や混乱を減らす工夫を。個室やパーソナルスペースの確保によりプライバシーを守り、不安感やストレスを緩和することで、暴言や暴力リスクを低減します。
コミュニケーション方法の工夫と専門職との連携
介護士のコミュニケーションスキルの向上
傾聴(アクティブリスニング)を意識し、相手の話を遮らずうなずきや言い換えで共感を示します。非言語コミュニケーション(表情やジェスチャー)を用いて安心感を与え、声のトーンや速度を調整し混乱を防ぎます。
また、短いセンテンスや具体的な指示を心がけ、利用者が理解しやすい言葉選びを徹底。日々の記録を共有し、成功例や失敗例をチームでフィードバックすることで、全職員の対応スキルを底上げします。
医師や専門職との連携によるアセスメント
ケアマネジャー、看護師、リハビリ職、臨床心理士と定期的なカンファレンスを実施し、多面的に利用者を評価します。薬物治療が必要なBPSDには医師と相談し、適切な投薬管理を行います。
心理士による認知機能検査や行動分析を用い、ストレス要因や行動パターンを可視化。環境要因との関連性を考慮した改善策を専門職チームで立案し、実践・検証を繰り返すことで継続的な質の向上を図ります。
家族との連携と理解促進
定期的な家族面談を設け、利用者の状態変化やケア方針を共有します。家族が抱える不安や負担をヒアリングし、一緒にケアプランを見直すことで支援の一体感を高めます。
認知症ケアやコミュニケーションの基本を紹介する家族向け勉強会を開催し、暴言や暴力が生じる背景を理解してもらいます。家族の協力を得ることで、訪問時や面会時の対応が一貫し、利用者の混乱や不安を軽減できます。
介護士自身の心を守るためのセルフケアと相談窓口
精神的な負担を軽減するセルフケアの方法
ストレスマネジメントの実践
介護業務では予期せぬトラブルや利用者の急変対応が続くため、日々のストレス蓄積を防ぐことが重要です。まずはマインドフルネス瞑想や深呼吸法を1日数分取り入れ、現在の感情や身体の緊張を客観視しましょう。
また、業務後に短い日報をつけ、起きた出来事と自分の感情を振り返ることでストレス要因を可視化できます。スーパーバイザーや同僚と定期的にケースカンファレンスを行い、悩みや課題を共有することで、ひとりで抱え込むリスクを減らせます。
さらに、EAP(従業員支援プログラム)や産業医面談を活用し、専門家のアドバイスを受けることで気づかなかった心理的負担に対する対処法を学べます。これらを継続的に実践することで、バーンアウト(燃え尽き症候群)を予防し、長期的に安定したメンタルヘルスを維持できます。
休息とリフレッシュの重要性
連続勤務や夜勤明けは心身に大きな負担となるため、十分な休息を計画的に取ることが欠かせません。厚生労働省が推奨する週休2日制や有給休暇の積極的な取得を心がけ、長時間労働を避けましょう。休日にはウォーキングやストレッチ、ヨガなどの軽い運動を取り入れることで、血流促進とともに脳内のリフレッシュが図れます。
また、趣味や家族との時間を大切にすることで仕事以外の自己価値感を高められます。短時間でも読書や音楽鑑賞、手芸など没頭できる活動を定期的に行い、業務外でのリラクゼーションを習慣化しましょう。
施設内外の相談窓口の活用
施設の相談窓口やハラスメント担当者
多くの介護施設ではハラスメント防止のために内部通報制度や相談窓口を設置しています。まずは所属施設の就業規則や労働協約を確認し、相談先の名称・連絡方法を把握しましょう。産業保健スタッフやハラスメント担当者に状況を具体的に伝える際は、暴言の日時・場所・状況を記録したメモや録音データを準備しておくと、適切な対応が迅速に行われやすくなります。
また、定期開催されるメンタルヘルス研修やスーパービジョン研修にも積極的に参加し、他職種や管理職とのネットワークを構築しておくことで、困ったときに相談しやすい環境を整えましょう。
外部の専門機関や労働相談窓口
施設内での解決が難しい場合は、外部機関の利用が有効です。全国にある各都道府県労働局の「ハラスメント相談窓口」や「職場のいじめ・嫌がらせ110番」では、法的観点や労働基準法に基づくアドバイスを無料で受けられます。
さらに、日本産業カウンセラー協会や基盤中央労働衛生協会の精神保健相談員によるカウンセリングを利用したり、EAPサービスを導入している場合は専門カウンセラーと定期面談を行うことで、第三者の立場から具体的な対処法やメンタルケア支援を得ることが可能です。
施設全体で取り組むべき暴言やハラスメント防止策
施設全体での風土づくりと体制整備により、利用者からの暴言やハラスメントによるストレスを軽減し、安全で安心できる介護環境を実現します。以下では、職員研修やマニュアルの整備、権利擁護の取り組みなど具体策を紹介します。
職員研修の実施とマニュアルの整備
定期的な研修と明確なマニュアルの整備は、介護士全員が同じ基準で対応できるようにするために欠かせません。
認知症ケアやコミュニケーションに関する研修
認知症高齢者の行動・心理症状(BPSD)への理解を深める研修を実施します。日本認知症ケア学会のガイドラインを参考に、アセスメントや傾聴技法、非言語コミュニケーションのロールプレイを取り入れることで、暴言を未然に防ぐコミュニケーションスキルを向上させます。
ハラスメント対応マニュアルの策定
暴言や暴力などのハラスメント事例を集約し、具体的な対応手順を明記したマニュアルを策定します。報告フロー、関係者への連絡先、緊急時の対応方法をわかりやすく図示し、全職員に配布・共有することで、一貫した対応を実現します。
介護士の権利擁護と安心して働ける環境づくり
介護士自身が安全に働き続けられるよう、メンタルケアや相談体制を充実させ、働きやすい職場風土を醸成します。
相談しやすい風通しの良い職場環境
管理職や相談窓口担当者を明確化し、匿名でも利用できるメール相談・オンライン面談制度を導入します。定期的に職場内アンケートを実施し、ストレス要因やハラスメント発生状況を把握して改善策を迅速に実行します。
介護士への定期的なヒアリングとサポート
月次の個別面談やグループミーティングを通じて、現場の悩みや困りごとを吸い上げます。心理的安全性を保つために、産業カウンセラーや社会福祉士によるメンタルヘルス研修を提供し、必要に応じて外部専門機関への相談窓口も案内します。
まとめ
介護現場では利用者からの暴言や暴力、性的ハラスメントが深刻な問題であり、認知症や精神疾患、環境ストレスなどが背景にあります。介護士は冷静な初期対応と迅速な報告が重要で、職場全体で情報共有やケアプランの見直し、コミュニケーション改善に努める必要があります。また、介護士自身のセルフケアや相談窓口の活用、職員研修やマニュアル整備による職場環境の改善も欠かせません。
メディケアキャリアで
北信越の介護職求人を探す
関連記事
-
訪問介護に向いている人の特徴とは?向き・不向きや必要なスキルを詳しく解説
訪問看護
知識
介護職
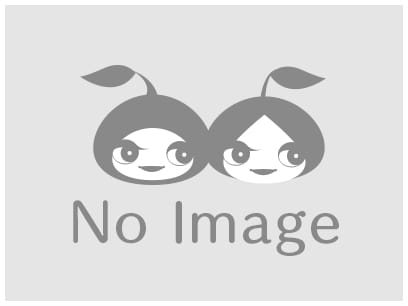
更新日:2025年11月22日
この記事では、訪問介護に向いている人の特徴や求められる資質を詳しく紹介します。
詳しく読む
-
訪問介護で出来る掃除の範囲はどこまで?
訪問看護
知識

更新日:2025年11月06日
この記事では、訪問介護サービスにおける掃除の業務範囲と具体的な作業例を、介護保険で認められる範囲と保険外の清掃内容に分けて丁寧に解説します。
詳しく読む
-
高校卒業と同時に介護福祉士資格取得を目指すには?
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
知識
介護職

更新日:2025年11月06日
本記事では、高卒から介護士・介護福祉士になるための流れや最短コース、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
詳しく読む
-
介護福祉士は勤続10年でいくら手当がもらえるか?
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
お金
知識
介護職

更新日:2025年11月06日
本記事では、勤続10年の介護福祉士がもらえる手当の種類や相場、収入を増やすためのポイントをわかりやすく解説します。
詳しく読む
-
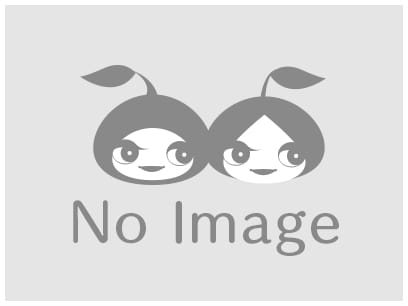
更新日:2025年11月22日
訪問介護に向いている人の特徴とは?向き・不向きや必要なスキルを詳しく解説
訪問看護
知識
介護職
この記事では、訪問介護に向いている人の特徴や求められる資質を詳しく紹介します。
詳しく読む -

更新日:2025年11月06日
訪問介護で出来る掃除の範囲はどこまで?
訪問看護
知識
この記事では、訪問介護サービスにおける掃除の業務範囲と具体的な作業例を、介護保険で認められる範囲と保険外の清掃内容に分けて丁寧に解説します。
詳しく読む -

更新日:2025年11月06日
高校卒業と同時に介護福祉士資格取得を目指すには?
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
知識
介護職
本記事では、高卒から介護士・介護福祉士になるための流れや最短コース、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
詳しく読む -

更新日:2025年11月06日
介護福祉士は勤続10年でいくら手当がもらえるか?
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
お金
知識
介護職
本記事では、勤続10年の介護福祉士がもらえる手当の種類や相場、収入を増やすためのポイントをわかりやすく解説します。
詳しく読む
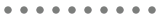

 0800-222-6155
0800-222-6155

 0800-222-6155
0800-222-6155