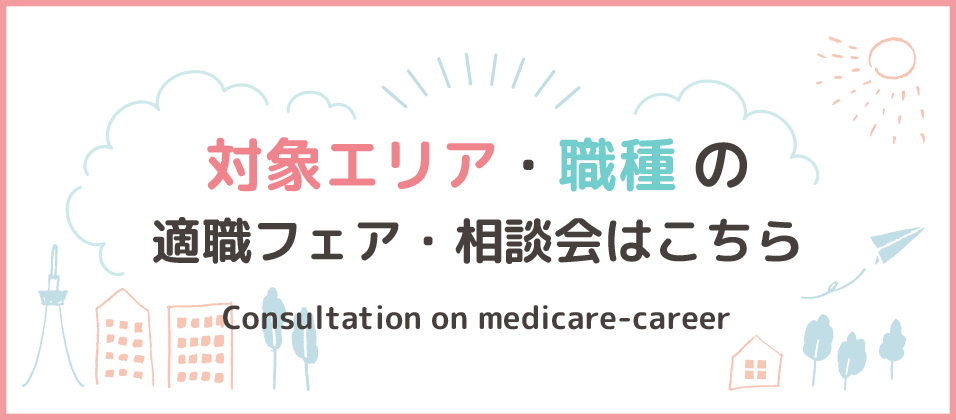介護コラム
介護士が現場で使ってはいけないNGワードとは?理由や言いかえも紹介
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
知識
介護職

介護現場では、日常的な言葉づかいが利用者の尊厳や安心感に大きく影響します。忙しさや疲労から無意識に使ってしまうNGワードは、信頼関係の崩壊や意欲の低下を招くリスクも。本記事では、介護士が避けるべき表現と言い換え例を紹介し、より丁寧で信頼されるコミュニケーションのあり方を解説します。
介護現場でNGワードが生まれる背景と重要性
日本は急速に高齢社会が進行し、介護現場では要介護者一人ひとりに寄り添ったケアが求められています。その一方で業務量の増加や人員不足、短い休憩時間といった過重労働が常態化し、職員同士のコミュニケーションもぎくしゃくしがちです。そのような環境では、無意識のうちに利用者の尊厳を損ねる「NGワード」が飛び出しやすくなります。
介護サービスの質を左右するのは、技術だけではなく言葉遣いです。利用者や家族との信頼関係を築くためには、言葉の選び方が極めて重要となります。NGワードの使用が続くと、利用者の安心感や自立支援の意欲を低下させるリスクがあるため、専門職として適切なコミュニケーションマナーを身につける必要があります。
なぜNGワードを学ぶ必要があるのか
まず、NGワードを学ぶことで「無自覚な心ない言葉」を減らし、職場全体のケア品質を向上させることができます。言葉遣いの改善は利用者満足度だけでなく、家族からの信頼獲得やチーム内の連携強化にもつながります。
次に、介護現場では認知症ケアや終末期ケアなど、繊細な配慮が求められる場面が多くあります。利用者の状態や心理に配慮した表現を選べないと、余計な不安や羞恥心を与えてしまい、ケアプラン通りの自立支援が難しくなることもあります。
さらに、NGワードを意識的に学ぶことで、職員自身のコミュニケーションスキル向上やメンタルヘルスの安定も期待できます。言葉を通じて安心感を伝えることで、ストレス軽減や職場のモチベーション維持にも寄与します。
言葉が利用者にもたらす影響
言葉は利用者の心身にダイレクトに働きかけます。尊厳を傷つける表現は自己肯定感を下げ、意欲の低下や不信感を招きやすくなります。例えば「どうせ無理でしょう」という決めつけの言葉は、自立訓練への取り組み意欲を著しく削いでしまいます。
逆に、肯定的で丁寧な言葉遣いは安心感を生み、信頼関係を深めます。「ご一緒にやってみましょう」「お手伝いさせてください」といった表現は、利用者の主体性を尊重しながら協働を促す効果があります。
また、言葉選び一つで認知症の方への誤解や混乱を防ぐことができます。簡潔で分かりやすい表現を心がけることで、不安感を和らげ、コミュニケーションエラーを減少させることが実証されています。
利用者の尊厳を傷つけるNGワードと代替表現
介護現場では言葉一つで利用者の自尊心や尊厳に大きな影響を与えます。配慮を欠いた表現は信頼関係を損ねるため、理解しやすく丁寧な言い換えを心掛けましょう。
上から目線に聞こえる言葉
「~してあげます」
NGワードの理由: 「~してあげる」という表現は利用者の主体性を奪い、恩着せがましく響くことがあります。代替表現: 「~いたします」「お手伝いいたします」など、敬語を用いて協力の姿勢を示しましょう。
「普通は~」
NGワードの理由: 一般論を押し付けると利用者の個別性が無視され、不快感を与えます。代替表現: 「多くの方は~」「一般的には~」など、柔らかい語調で状況を伝えましょう。
子ども扱いする言葉
「おじいちゃん、おばあちゃん」
NGワードの理由: 親しみを装いつつも敬意に欠ける呼び方は、相手を大人として尊重していない印象を与えます。代替表現: 「○○様」「おじいさま」「おばあさま」など、敬称を用いて丁寧に呼びかけましょう。
「あらあら、いい子ですね」
NGワードの理由: 子どもに話しかけるような語り口は利用者を子ども扱いし、尊厳を傷つけます。代替表現: 「お上手ですね」「素晴らしいですね」など、丁寧で前向きな声かけを行いましょう。
決めつけや否定的な言葉
「どうせできませんよ」
NGワードの理由: はじめから否定的な見方を示すことで利用者の意欲を低下させ、自尊心を傷つけます。代替表現: 「一緒にチャレンジしてみましょうか」「ゆっくり進めていきましょう」など、励ましの言葉を選びましょう。
「なんでできないんですか」
NGワードの理由: 問い詰めるような口調は利用者を責める印象を与え、不安やストレスを引き起こします。代替表現: 「どのあたりがお辛いでしょうか」「何かお手伝いできることはありますか」など、共感とサポートを示しましょう。
専門職として不適切な印象を与えるNGワードと代替表現
無責任に聞こえる言葉
「私にはわかりません」
利用者やご家族に対して「わからない」と伝えると、責任を放棄している印象を与えます。代わりに「確認して折り返しご連絡いたします」と言い換えることで、調査・報告のプロセスを明示し、信頼感を高められます。
「聞いていません」
情報共有が不十分であることを露呈し、チームワークや専門性への不安を招きます。代替表現としては「すみません、こちら確認が遅れていました。すぐに調べてご報告します」と述べ、改善意欲と責任感を示しましょう。
プライベートな感情を露わにする言葉
「疲れた」「しんどい」
感情をストレートに表現すると利用者に負担を感じさせ、安心感を損なう恐れがあります。代わりに「少し休憩をいただいてもよろしいでしょうか」「体調を整えてから再度対応いたします」と伝え、プロとしての自己管理意識を示しましょう。
「面倒くさい」
業務へのネガティブな印象をそのまま口にすると、プロ意識の欠如と受け取られかねません。「対応に工夫が必要ですが、最善を尽くします」「効率的な方法を考えて進めます」と前向きな姿勢を言い換えに用いると良いでしょう。
専門用語の乱用や省略語
「ADLが低いので」
専門用語をそのまま使うと、利用者やご家族に説明不足と思われやすいです。「日常生活動作で介助が必要な場面がありますので」と平易な言葉に直し、状況を具体的に伝えることが大切です。
「特変なしです」
省略した表現は情報の抜け漏れや事務的な印象を与えます。「現在、大きな変化やリスクは確認されておりません」と詳細を加えて伝えることで、安心感と専門性を両立できます。
家族や同僚との関係性を損ねるNGワードと代替表現
家族や同僚との円滑なコミュニケーションは、介護サービスの質を左右します。ここでは、関係性を悪化させやすいNGワードと、その代わりに使いたい表現を具体的にご紹介します。
家族への不適切な言葉
「いつも来ないですね」
この言葉は家族の来訪頻度を責める印象を与え、感謝の気持ちを伝えられません。代替表現としては、「お忙しい中お越しいただき、ありがとうございます。本日はどんなお話をお聞かせいただけますか?」と、感謝と関心を合わせて伝えると良いでしょう。
「もっと家で見てあげてください」
直接的な指示は家族の負担感を増し、反発を招く恐れがあります。代わりに、「ご自宅でのサポートについてご不安な点やご希望があれば、お気軽にご相談ください。一緒に方法を検討いたします」と、協力の姿勢を示す言葉を用いることをおすすめします。
同僚への不満や愚痴
「あの人使えない」
個人を否定する発言はチームワークを損ない、職場の雰囲気を悪化させます。代わりに、「〇〇さんの得意分野を活かしていただけると助かります。一緒に役割分担を見直しませんか?」と、互いの強みを尊重しながら改善策を提案しましょう。
「私の仕事じゃない」
責任回避の印象を与え、職場内の信頼関係を損ないます。代替表現としては、「まずは誰が担当かを確認し、必要であれば私もサポートいたします。お手伝いできることがあればお知らせください」と、自発的な協力意欲を示すのが効果的です。
NGワードを避けるためのコミュニケーション術
傾聴と共感の姿勢
まずは利用者の話にしっかり耳を傾け、気持ちを受け止める姿勢が大切です。目線を合わせ、相手の呼吸や表情に注意を払いながら話を聞くことで、安心感を高められます。
話の途中で遮らずに最後まで聞き、言葉の裏にある感情を読み取る「アクティブリスニング」を意識しましょう。「つらかったですね」「不安だったのですね」といった相槌を入れることで、利用者は自分の思いを尊重されたと感じます。
また、聞き返しや要約も効果的です。「〇〇というお気持ちでいらっしゃったのですね?」と確認することで、誤解を減らし、信頼関係を深めることができます。
ポジティブな言葉選びの習慣
日常的に「できない」「難しい」といった否定的な表現を避け、前向きな言葉に言いかえる習慣をつけましょう。例えば「歩けませんか?」ではなく「今日はここまで一緒に歩けそうですか?」と問いかけることで、挑戦意欲を引き出せます。
肯定的な表現には、利用者の自尊心を支える効果があります。「頑張ったね」「とても上手にできましたね」という声かけを繰り返すことで、自己肯定感を育み、介護への協力姿勢も高まります。
また、感謝や賞賛を具体的に伝えると、利用者だけでなく家族や同僚との関係も円滑になります。「本日は早起きしていただき、ありがとうございました」といった言葉は、職場全体の雰囲気向上にも寄与します。
状況に応じた声かけの工夫
利用者の体調や気分に合わせて、声のトーンやスピードを調整しましょう。元気そうなときは明るくハキハキと、疲れているときはゆったりした優しい声で話すことで、安心感が違います。
指示やお願いをするときは、一度に複数の項目を伝えず、短い文で区切りながら要点を示します。「まず手を洗いましょう。それから椅子に座って呼吸を整えましょう」というように、段階的に声かけすることで混乱を防げます。
必要に応じて選択肢を提示し、主体性を尊重する言い回しにすることも有効です。「お茶は温かいものと冷たいもの、どちらがよろしいですか?」と尋ねることで、利用者が自分で意思決定できる環境をつくれます。
さらに、軽いスキンシップ(手を添える、背中を軽くさするなど)を交えながら声をかけると、言葉だけでは伝わりにくい安心感や温もりを届けられます。ただし、相手の心身の状態やパーソナルスペースを尊重しながら行いましょう。
介護士のNGワードをなくすために日頃からできること
チーム内での情報共有と振り返り
日々の業務終了時やシフト交替時に、利用者への対応で気になった言葉遣いや場面をチームで共有しましょう。ケア会議や朝礼で具体的な事例を挙げ、「こんな言い方ならどうか」「こう言い換えると尊厳を守れる」など、実践的な振り返りを行うことでNGワードの定着を防ぎます。
共有にあたってはホワイトボードや電子カルテのメモ欄を活用し、誰でも参照・追記できる仕組みをつくると効果的です。また、月に一度の事例検討会では、言葉選びのポイントや代替表現をロールプレイ形式で確認し、チーム全体の意識向上を図りましょう。
研修や勉強会への参加
介護現場でのコミュニケーションスキル向上を目的とした研修や勉強会に定期的に参加しましょう。社内研修のほか、地域包括支援センターや自治体が主催する認知症ケア研修、利用者の尊厳を学ぶワークショップなどを受講することで、最新の言葉遣い事例や専門家の視点を取り入れられます。
eラーニングやオンラインセミナーも活用し、勤務の合間に自身のペースで学習すると継続しやすくなります。新人だけでなくベテラン職員も参加することで、組織全体で共通認識を高め、NGワード対策を組織文化として根付かせましょう。
自己肯定感を高める意識
自分自身の気持ちに向き合い、日頃からポジティブな言葉を使う習慣をつくることで、利用者や同僚に対しても自然と肯定的な声掛けができるようになります。業務後に「今日は○○がうまくできた」「こんな声掛けで利用者が笑顔になった」といった成功体験を振り返り、記録しておくことが効果的です。
また、同僚や上司からのフィードバックを積極的に受け入れ、小さな成功や改善点を共有し合うことで相互に自己肯定感を高めましょう。自己評価だけでなく、チームメンバーからの承認が自己肯定感を支え、結果として無意識のうちにNGワードを避ける言葉選びにつながります。
まとめ
介護士が現場で使うNGワードは利用者の尊厳や信頼を損ね、専門性やチームワークにも影響します。言いかえや傾聴・共感を意識し、研修や振り返りで日々改善を重ね、質の高いケアを提供しましょう。
メディケアキャリアで
北信越の介護職求人を探す
関連記事
-
未経験でも介護士として働くことは可能?
介護福祉士
ケアマネージャー
仕事内容
知識
介護職

更新日:2026年01月29日
この記事では、未経験者が歓迎される理由や仕事内容、資格取得のステップ、職場選びのポイントまでをわかりやすく解説します。
詳しく読む
-
病院に勤務する介護士の仕事内容とは?
介護福祉士
ケアマネージャー
仕事内容
知識
介護職

更新日:2026年01月23日
この記事では、病院勤務の介護士の具体的な仕事内容、日勤・夜勤の流れ、多職種との連携、他施設との違い、必要な資格やスキル、キャリアパスなどを解説。
詳しく読む
-
介護職に復職した時に最大40万円もらえる再就職準備金とは?
介護福祉士
ケアマネージャー
お金
知識
介護職

更新日:2026年01月23日
本記事では再就職準備金制度の概要や申請方法、注意点を詳しく解説します。
詳しく読む
-
介護士はどの年齢層が多い?年代別の特徴や働き方の違いなども解説
介護福祉士
ケアマネージャー
知識
介護職

更新日:2026年01月23日
この記事では、年代別の特徴や働き方の違い、施設形態・雇用形態による傾向を詳しく解説します。
詳しく読む
-

更新日:2026年01月29日
未経験でも介護士として働くことは可能?
介護福祉士
ケアマネージャー
仕事内容
知識
介護職
この記事では、未経験者が歓迎される理由や仕事内容、資格取得のステップ、職場選びのポイントまでをわかりやすく解説します。
詳しく読む -

更新日:2026年01月23日
病院に勤務する介護士の仕事内容とは?
介護福祉士
ケアマネージャー
仕事内容
知識
介護職
この記事では、病院勤務の介護士の具体的な仕事内容、日勤・夜勤の流れ、多職種との連携、他施設との違い、必要な資格やスキル、キャリアパスなどを解説。
詳しく読む -

更新日:2026年01月23日
介護職に復職した時に最大40万円もらえる再就職準備金とは?
介護福祉士
ケアマネージャー
お金
知識
介護職
本記事では再就職準備金制度の概要や申請方法、注意点を詳しく解説します。
詳しく読む -

更新日:2026年01月23日
介護士はどの年齢層が多い?年代別の特徴や働き方の違いなども解説
介護福祉士
ケアマネージャー
知識
介護職
この記事では、年代別の特徴や働き方の違い、施設形態・雇用形態による傾向を詳しく解説します。
詳しく読む
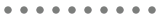

 0800-222-6155
0800-222-6155

 0800-222-6155
0800-222-6155