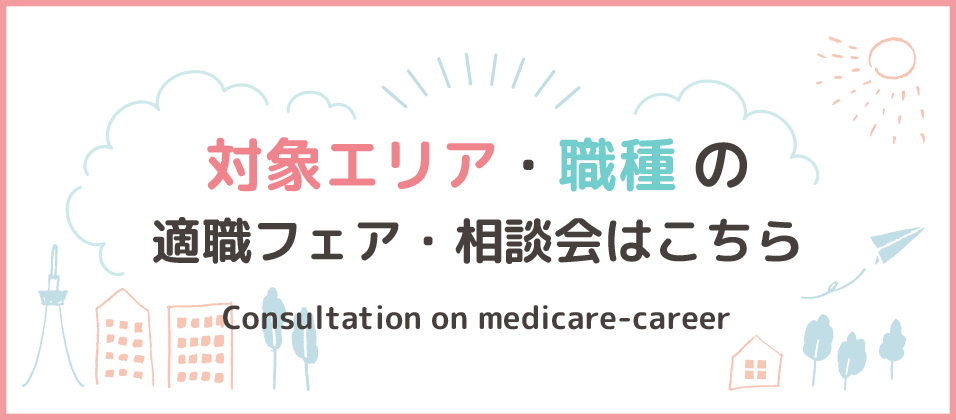介護コラム
ホームヘルパー2級と初任者研修は何が違う?資格の取得方法まで解説
介護福祉士
介護職

高齢化社会が加速する日本において、介護職員は大きな需要のある職業といえるでしょう。需要がある分、安定して長く働けるというメリットもあります。 介護職に就きたいと考えたとき、よく耳にするのが「ホームヘルパー2級」と「初任者研修」という二つの資格です。どのような違いがあるのかわからず悩んでしまう方も多いかもしれません。資格の有無が就職に有利に働くこともあるので、しっかりと理解しておきたいですよね。 この記事ではホームヘルパー2級と初任者研修の違いや、どうすれば取得できるかについてお伝えしていきます。
ホームヘルパー2級と初任者研修の違い

初任者研修は正式名称を「介護職員初任者研修」といい、平成25年4月1日の介護保険法施行規則改正時に作られた資格です。3級から1級まであったホームヘルパーはそのとき廃止されました。
ホームヘルパー2級とは
ホームヘルパー2級は訪問介護を目的とした、介護職員育成のために作られた資格です。介護を必要としている方の、自宅での生活支援や身体介護ができます。
初任者研修とは
初任者研修は訪問介護だけでなく、施設などでの介護にも対応できる介護職員の育成を目的とした資格です。すでにホームヘルパー2級を取得していれば、初任者研修と同等の介護知識を習得していると見なされます。そのため改めて初任者研修を取得する必要はありません。
なぜホームヘルパー2級は廃止され初任者研修となったのか
ホームヘルパー2級と初任者研修は資格取得課程のカリキュラムにも大きな違いはなく、なぜ新しい資格に変更する必要があったのか気になるところです。詳しく見ていきましょう。
幅広い場所で活躍できる介護職員の育成
平成28年度版の厚生労働白書を見ると、1995年頃を境に14歳以下の人口割合と65歳以上の人口割合が逆転し、年々高齢者の人口割合が増加していることがわかります。
介護職員のニーズは高まり、介護を必要とする場面は増えてきました。そのため資格の汎用性を高める必要があったのです。あらゆる介護現場に対応できるよう、初任者研修が作られたといえます。
介護職員のキャリアパスを明確化するため
介護職員としてのキャリアを見据え、将来的には国家資格である介護福祉士の取得を目指す人もいるでしょう。この介護福祉士を取得するためにはさまざまなルートがあります。
それぞれのルートによって受験のための必要資格が異なるなど、その仕組みはとても複雑です。
初任者研修はいわば介護職員としての、基礎的な知識を得られる資格です。そこからさらにキャリアを目指すなら「実務者研修」を取得します。
現在では実務経験3年以上に加え「実務者研修」を取得すれば、介護現場での経験を元に資格取得を目指す「実務経験ルート」での介護福祉士の受験資格を得られます。非常に明確なキャリアパスが形成されたことにより、介護職員としての目標を持ちやすくなったといえるでしょう。
実際に介護現場で働くときの影響
ホームヘルパー2級と初任者研修はどちらを取得していても、現在の介護現場でできる仕事は同じです。もちろんすべての介護現場において働くことができます。どちらも正式な介護の資格として認められているので、就職活動の際にも影響することはありません。
細かく見るとそれぞれの資格で学習したカリキュラムには、多少違いがあります。しかしその学習内容違いで実務に大きな影響を及ぼすことはありません。
初任者研修取得でできる仕事
初任者研修を取得すれば、介護を必要とする高齢者に実際触れて介助を行う「身体介護」ができるようになります。身体介護には次のようなものがあります。
- 食事の介助
- 入浴の介助(全身入浴、顔や髪などの部分的な洗浄)
- 排泄の介助
- 着替えの介助
- 寝返りなど体勢変換の介助
- ベッドから車椅子への移乗
- そのほか移動の際など介助が必要な方へのサポート
- 服薬の介助
初任者研修を取得していれば、身体介護を含めた介護全般に対応できます。介護施設だけでなく看護助手としても、この資格の保持者は歓迎されます。看護助手の仕事は看護師の事務的な補助だけではありません。患者さんの身の回りのケアなども含まれるため、初任者研修で得た知識を生かすことができるのです。
初任者研修の取得の仕方とカリキュラム

初任者研修は取得したいと思えば誰でも挑戦できる資格です。ではどのようにすれば取得できるのか、取得の仕方と期間、カリキュラムの内容についてみていきましょう。
初任者研修の取得方法
初任者研修を取得するためには、講義と演習の10項目のカリキュラムで構成される、約130時間の研修を受ける必要があります。全カリキュラム修了後には修了試験があり、これに合格しなければなりません。
これらの研修を受ける方法には「通信講座」「通学講座」の2種類があります。
- 通信講座
自宅にいながら参考書やテキストによる勉強が可能です。仕事や育児などで忙しく通学が難しい方にとっては、とても便利は取得方法といえるでしょう。しかし通信課程による自宅などでの学習時間は、40.5時間が上限と定められています。残りの89.5時間はスクーリング(教室での講義)を受けなければならないことを覚えておきましょう。
- 通学講座
資格取得スクールなどに通い取得する方法です。
しっかりと時間を取れる方には、短期で集中的に学習できるので便利といえます。
取得期間
全日制で通えるものから、週に数回、または土曜日だけといった通学の仕方など、スクールによってさまざまな体系が用意されています。
例えば1日に5時間の講習を受け、週に5日通ったとすれば1~2ヶ月程度で習得でき、1日に5時間の講習を週に1回の場合は4~5ヶ月ほどかかることになります。当然ながら全日制の方が早く取得できます。
通信講座の場合は、自宅での学習を計画的に配分する必要があります。
初任者研修のカリキュラム
厚生労働省の定める初任者研修に必要な研修課程カリキュラムと時間は次のとおりです。
| 科目名 | 合計時間 | |
| 1 | 職務の理解 | 6時間 |
| 2 | 介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 |
| 3 | 介護の基本 | 6時間 |
| 4 | 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 9時間 |
| 5 | 介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
| 6 | 老化の理解 | 6時間 |
| 7 | 認知症の理解 | 6時間 |
| 8 | 障害の理解 | 3時間 |
| 9 | こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 |
| 10 | 振り返り | 4時間 |
| 合計 | 130時間 |
※研修後1時間程度の修了試験
ヘルパー2級では講義・実技・実習のカリキュラムが明確に分かれていたのに対し、初任者研修では講義と実習を一体的に行うようになっています。「職務の理解」「振り返り」において、職場見学など実際の介護現場体験が必要に応じて行われます。
介護職をめざすならまずは初任者研修を
ホームヘルパー2級は介護保険法施行規則の改正によって初任者研修へと移行しました。初任者研修は時代のニーズに合わせたカリキュラムによって、さまざまな介護の現場に対応できるような資格になっています。
介護の現場で働きたいと考えているなら、まずは初任者研修を取得してみましょう。介護に携わるための基礎知識を得られるので、介護施設だけでなくさまざまな場所へ就職の窓口が広がります。
メディケアキャリアで
北信越の介護職求人を探す
関連記事
-
訪問介護に向いている人の特徴とは?向き・不向きや必要なスキルを詳しく解説
訪問看護
知識
介護職
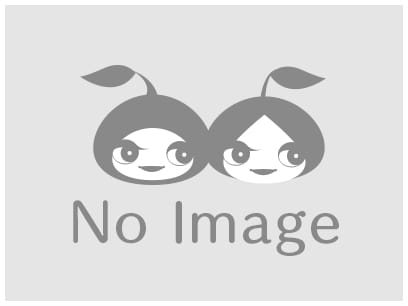
更新日:2025年11月22日
この記事では、訪問介護に向いている人の特徴や求められる資質を詳しく紹介します。
詳しく読む
-
高校卒業と同時に介護福祉士資格取得を目指すには?
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
知識
介護職

更新日:2025年11月06日
本記事では、高卒から介護士・介護福祉士になるための流れや最短コース、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
詳しく読む
-
介護福祉士は勤続10年でいくら手当がもらえるか?
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
お金
知識
介護職

更新日:2025年11月06日
本記事では、勤続10年の介護福祉士がもらえる手当の種類や相場、収入を増やすためのポイントをわかりやすく解説します。
詳しく読む
-
介護士をやめたい理由TOP10と解決策を紹介
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
知識
介護職

更新日:2025年11月04日
本記事では、多くの介護士が退職を考える理由TOP10をランキング形式で紹介します。
詳しく読む
-
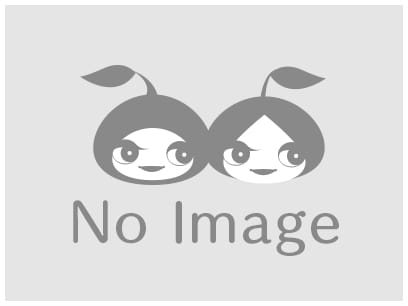
更新日:2025年11月22日
訪問介護に向いている人の特徴とは?向き・不向きや必要なスキルを詳しく解説
訪問看護
知識
介護職
この記事では、訪問介護に向いている人の特徴や求められる資質を詳しく紹介します。
詳しく読む -

更新日:2025年11月06日
高校卒業と同時に介護福祉士資格取得を目指すには?
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
知識
介護職
本記事では、高卒から介護士・介護福祉士になるための流れや最短コース、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。
詳しく読む -

更新日:2025年11月06日
介護福祉士は勤続10年でいくら手当がもらえるか?
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
お金
知識
介護職
本記事では、勤続10年の介護福祉士がもらえる手当の種類や相場、収入を増やすためのポイントをわかりやすく解説します。
詳しく読む -

更新日:2025年11月04日
介護士をやめたい理由TOP10と解決策を紹介
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
知識
介護職
本記事では、多くの介護士が退職を考える理由TOP10をランキング形式で紹介します。
詳しく読む
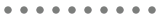

 0800-222-6155
0800-222-6155

 0800-222-6155
0800-222-6155